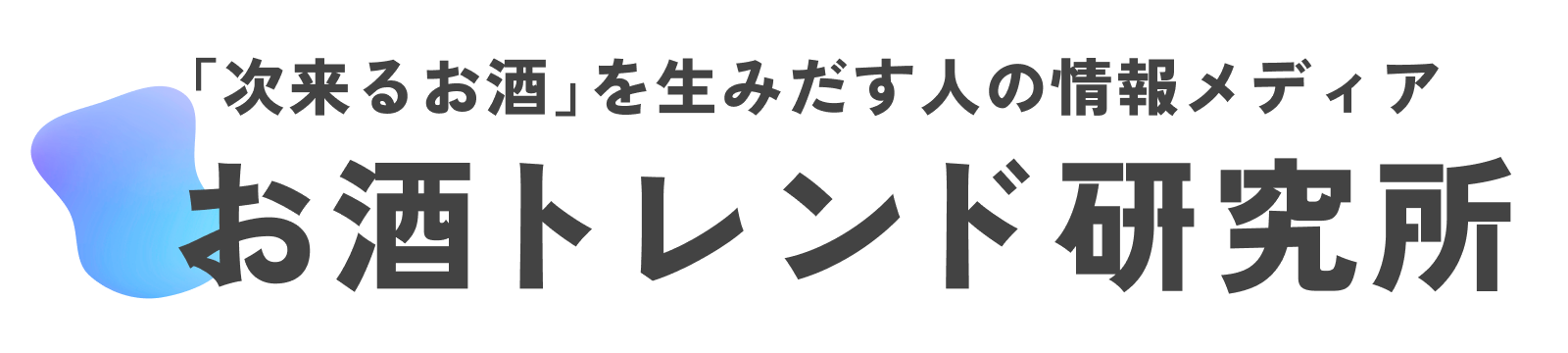Z世代は“飲まない”わけじゃない?「アゲ⇔チル」を行き来する新時代の飲酒スタイルと商品開発の可能性
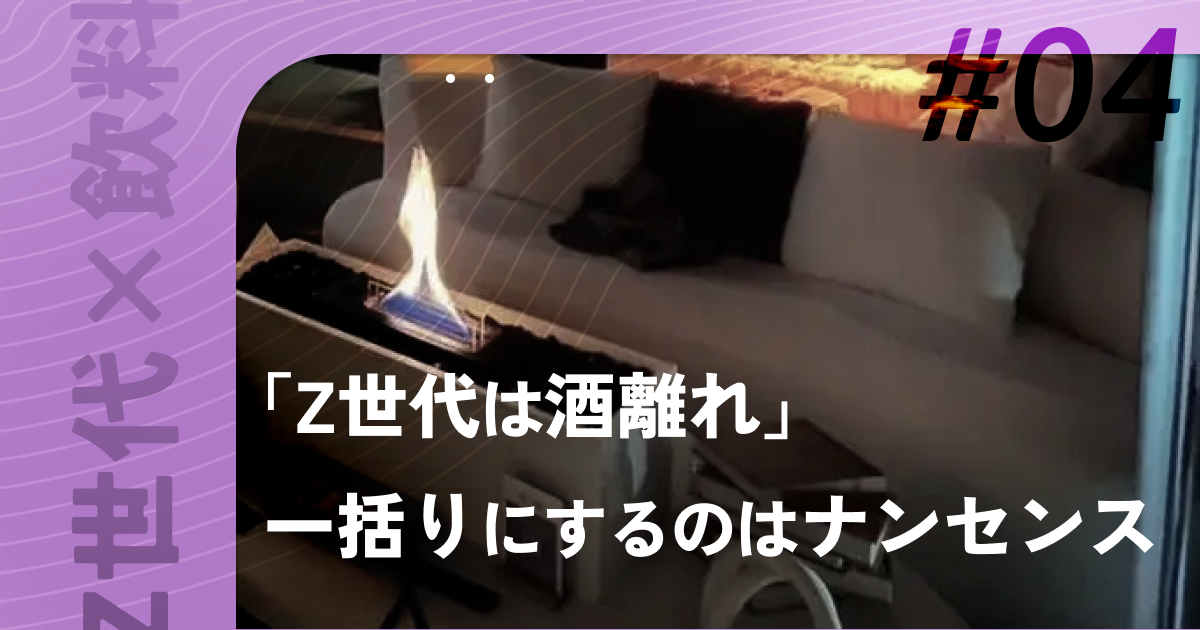
「近頃の若者はお酒を飲まなくなった」。
そんな言葉を耳にすると、確かに居酒屋での“飲みニケーション”や無理な一気飲みが減っている印象を受けるかもしれません。しかし、“まったく飲まない”という意味ではありません。
Z世代が求めているのは、いわゆる「場当たり的に酔う」スタイルではなく、テンションを上げたいときには盛り上がりを、落ち着きたいときにはリラックスを求める、いわば“アゲ飲み”と“チル飲み”をシーンごとに使い分ける柔軟性と考えています。
SNS上でもそうした飲み方の片鱗は見え隠れしています。
大人数でワイワイやっている写真は、クローズドな友達内のストーリーで共有し、夜カフェやシーシャバーでゆっくり過ごしている写真はパブリックに公開するなど、投稿する場を分けているケースは珍しくありません。そこには「SNSを常時見ている人が不快にならないだろうか」と周囲に配慮するZ世代ならではの気遣いも表れています。
こうしたZ世代の飲酒スタイルから見えてくるのは、単に「若者が酒離れしている」という一括りでは説明できない、新しい飲み方の選択肢の多様化です。本記事では、そんな“アゲ飲み”と“チル飲み”の実態をひも解きながら、コロナ禍以降に生まれた飲み方の自由度や、デジタルネイティブならではの周囲への配慮意識を取り上げます。
最後には、このトレンドを商品企画に活かすためのヒントを整理しましたので、ぜひ参考にしてみてください。
「アゲ飲み」と「チル飲み」を使い分けるZ世代
「Z世代=酒離れ」のイメージは本当か?
まず見直したいのは、「Z世代はお酒をほとんど飲まない」という先入観です。
たしかに、昭和〜平成に根強かった“飲みニケーション”のような文化には距離を置いているかもしれません。上下関係に縛られた飲み会や、深夜まで酔い潰れるような宴席を“ダルい”と感じる若者も少なくないでしょう。
しかし、だからといって「お酒をまったく飲まない」わけではありません。実際には、“自分が心地よいと感じる相手や空間でなら、むしろ積極的に楽しむ”というZ世代ならではのスタンスが目立ちます。
その背景には、コロナ禍の影響も見逃せません。
外出自粛や会食制限により、強制的に“飲みに行かなくてもいい”日々が続いた結果、「今日は飲みたい気分だから飲む」「この人たちとなら飲みたい」といった“選べる飲酒スタイル”が当たり前になったのです。
たとえば、
- 友人同士でゆっくり語りたい日は“チル飲み”
- ストレス発散したい日は“アゲ飲み”
といったように、シーンや気分によって飲み方を使い分けるという新しい習慣がZ世代には定着しつつあります。
盛り上がりたいときは“アゲ飲み”
Z世代が“アゲ飲み”を選ぶのは、テンションを上げたい日や、仲間との一体感を楽しみたいとき。
たとえば音楽フェスでアルコール片手に踊ったり、推し活仲間とライブ帰りに乾杯したり、居酒屋で友人とワイワイ語らったり。飲む目的が“社交”というより、“気分を高める手段”に近いのが特徴です。
とはいえ、全力で盛り上がる一方で、Z世代ならではの“配慮”も忘れません。
大騒ぎしている動画や酔い潰れた写真をSNSに全体公開するのはNG。
「恥ずかしい」と捉えられるリスクがあるため、アゲ飲みの様子を投稿する場合は、
- close friends(インスタの親しい友達機能)だけに共有
- ストーリーズに軽く載せてすぐ消す
- “おしゃれに見える範囲だけ”を切り取ってアップ
といったように、シーンに応じて投稿先や見せ方を工夫する傾向があります。
つまり、「はっちゃけたいけど、TPOや人間関係はわきまえる」というバランス感覚を持ったアゲ飲みがZ世代流なのです。
癒やしを求めるときは“チル飲み”
一方、“チル飲み”は心身を整えたいときや、じっくり語りたい夜に選ばれます。
Z世代にとっての“飲み時間”は、リフレッシュや自己回復の時間でもあります。
たとえばこんなシーンが人気。
- 夜カフェでのコーヒーリキュールやクラフトジン
- シーシャバーでゆったり話しながら一杯
- 公園でホットワインを楽しむ“夜ピク(夜ピクニック)”
- おうちでお気に入りのグラスと推しアニメを並べて一人飲み
いずれも共通しているのは、「自分の世界に没入できる空間」であること。
しかも、こうした空間は“映える”要素も満載。
パッケージがかわいいお酒や、間接照明とガラスの映り込みが美しいグラスなど、ビジュアル重視のZ世代にとってSNS映えしやすいのも魅力の一つです。
また、“チル飲み”の写真はパブリックに投稿しやすいため、「今日はこんな素敵な時間を過ごしてます」というさりげない自己表現のツールにもなっています。
コロナ禍とデジタルネイティブ意識が生んだ飲み方の多様
コロナ以前は、「飲み会には参加するのがマナー」「空気を読んで盛り上げるのが正義」といった暗黙のルールが存在しました。
しかし、コロナ禍を経て、「行きたくないときは行かなくてもいい」「自分のペースで楽しめばいい」という空気が社会全体に広がりました。
そして、Z世代はデジタルネイティブとして、SNSを介したコミュニケーションを幼い頃から当たり前に行ってきた世代。
リアルな場でも「その場にいる人」「その場にいないSNSのフォロワー」両方への配慮が自然にできるのです。
その結果が、
- 大騒ぎしたい日は“アゲ飲み”(でも閉じたSNSにシェア)
- 癒やされたい日は“チル飲み”(オープンなSNSにもアップOK)
という飲み方の最適化に繋がっていると言えるでしょう。
商品企画への活用アイデア|アゲ⇔チルを自在に行き来できる仕組みづくり
ここまで見てきたように、Z世代はそのときの気分や状況に合わせて、ハイテンションで盛り上がる“アゲ飲み”と、落ち着いて楽しむ“チル飲み”を切り替える柔軟さを持っています。こうした特徴は、飲料商品企画にも大いに活かせるはずです。「盛り上がりたい日もあれば、落ち着きたい日もある」というニーズを前提に、これらに対して幅を持って応えられるアイデアを考えてみましょう。
まとめ:Z世代に寄り添う“アゲ⇔チル”の柔軟性こそ企画の鍵
Z世代は「お酒自体を避けている」のではなく、だれと・どこで・どんな気分で飲むかを繊細に使い分けています。ワイワイと大勢でアゲたいときもあれば、一人や少人数でチルタイムを満喫したいときもあるという、多様なモードを自在に行き来するのです。この背景にはコロナ禍を経て生まれた飲み方の自由度や、SNS文化の中で常に周囲との調和を図ろうとするデジタルネイティブ意識があるといえます。
こうした変化を前提に、商品企画の現場でできることは意外にも多くあります。ブランドストーリーで“あなたの毎日に寄り添う”姿勢を示す、モードチェンジ可能な商品設計で“一杯で二度美味しい”体験を提供する、あるいは専用アプリを使ってユーザーがその日の気分を記録し、最適な飲み方を見つけられるように支援する──どれもZ世代の柔軟な消費スタイルに合致したアイデアとなるでしょう。
「アゲ飲みとチル飲みを同じユーザーが行き来する」という視点を盛り込むだけで、これまでになかった商品開発やマーケティングの可能性が広がります。ぜひ、Z世代のリアルな嗜好や行動パターンを活かした企画づくりに挑戦してみてはいかがでしょうか。飲料を通じて、彼らが“アゲ”と“チル”を自由に切り替えながら豊かな時間を過ごせるような提案ができれば、Z世代の心をしっかりとつかむ新たなブランドが誕生するかもしれません。
SEAMは、自社ブランドを通して、Z世代を中心としたお酒の楽しみ方に関する調査、分析を行ってきました。若年層向けのドリンク商品をお考えの際は、お気軽にご相談ください。