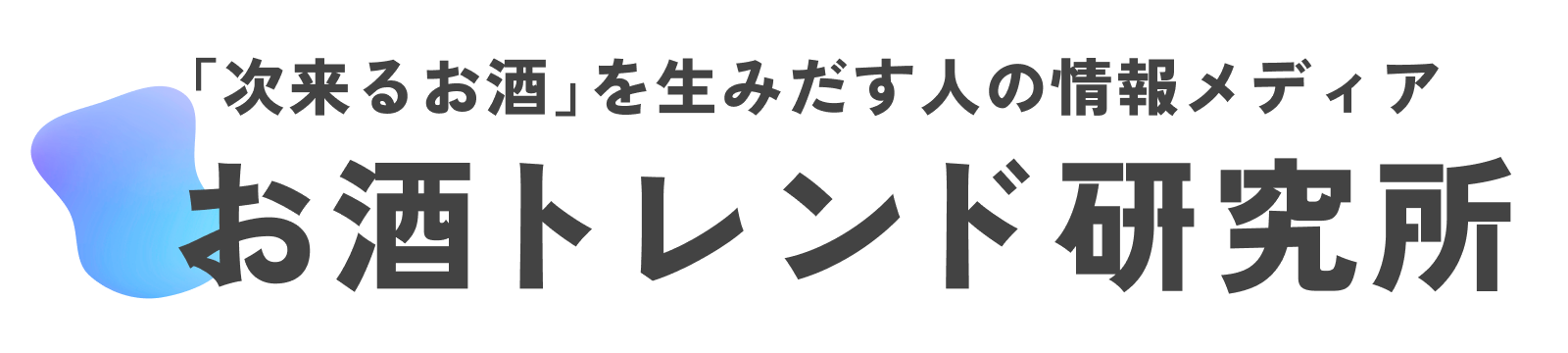口コミ・UGCを活用したブランド認知度向上|ユーザーが自発的に発信したくなる仕掛けと実践法
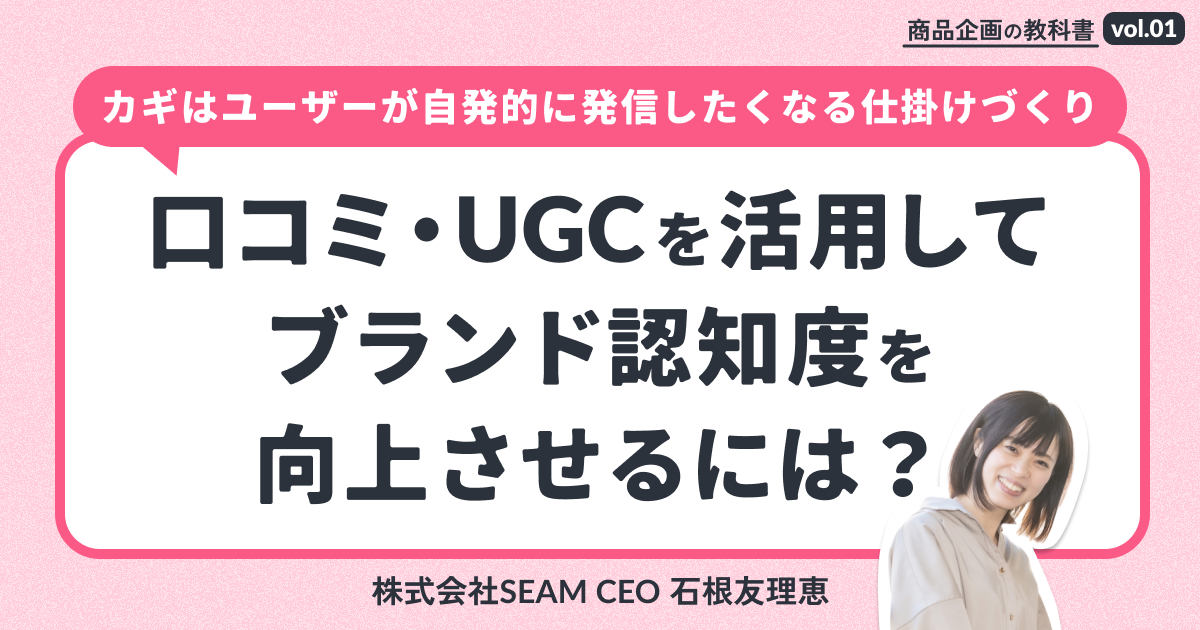
「SNSやレビューサイトで自然と口コミが広がる商品を作りたい」「ユーザーが自発的にシェアしたくなる仕掛けを知りたい」と悩んだことはありませんか?
従来の広告やプロモーションだけでは、Z世代やミレニアル世代の心をつかむのは難しくなっています。特に現代の消費者は、企業発信の情報よりもUGC(ユーザー生成コンテンツ)のようなリアルな声や体験談を信頼する傾向が強まっています。
では、どのようにしてUGCを促進し、商品認知度を向上させることができるのでしょうか?
本記事では、飲料プロデュース事業で若年層向け商品の開発や共創型マーケティングを実践してきたSEAMの知見をもとに、ユーザーが自発的に発信したくなる心理や、その心理を刺激するブランド体験の作り方、さらに実践的なUGC促進アプローチと成功事例を解説します。
- UGCが現代マーケティングにおいて重要視される理由
- ユーザーが「シェアしたくなる瞬間」の心理とその仕掛け
- 自然とUGCが生まれるブランド体験とSNS戦略
- 成功事例に学ぶUGC活用法と売上拡大のヒント
「SNSを活用した口コミ戦略を取り入れたい方」や「ターゲットのインサイトを深掘りしてUGCを活用したヒット商品を生み出したい方」にとって参考になる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
UGCとは?飲料業界で注目される理由
UGC(User Generated Content)の定義
UGCとは「ユーザー生成コンテンツ」の略称で、企業ではなく消費者であるユーザーが自発的に作成・発信するコンテンツ全般を指します。
- 商品を購入したユーザーがSNSに投稿した写真や動画
- Xでのつぶやき
- 口コミサイトへのレビュー
- ブログでの体験談
企業が制作した広告や公式情報ではなく、一般のユーザーの生の声やビジュアルが含まれる点が特徴です。
身近な例を挙げれば、Instagramにお気に入りのドリンクの写真を投稿する、Twitterで新発売の飲み物の感想をつぶやく、ECサイトの商品ページにレビューを書く、といった行為はすべてUGCです。
企業主導の情報発信に比べ、UGCはユーザー自身の言葉で語られるためリアリティや親近感があり、見る人にとって信頼性が高いと感じられやすいのがメリットです。
なぜ今、飲料業界でUGCが重要視されているのか
飲料業界でUGCが注目される背景には、消費者の情報収集や購買行動の変化があります。
検索エンジンではなくSNSで情報収集する消費者
スマートフォンとSNSが普及した現在、ユーザーは商品を知る際に検索エンジンだけでなくSNS上の口コミや投稿(UGC)も参照するようになりました。
「ググるからタグるへ」と言われるように、ハッシュタグ検索で実際の利用シーンや評判を調べる消費者が増えているのです。
特に若年層ほどその傾向が強く、Z世代は企業公式の発信よりも同世代のリアルな投稿を信頼する傾向があり、生活者の64.6%が購買行動においてUGCを信頼するとする調査結果もあります(生活者の64.6%が購買行動においてUGCを信頼、購入の意思決定に最も影響を与えるコンテンツ形式は、「テキスト」)。
この数字は年々上昇しており、特に30代以下の若年層や女性でUGCへの信頼度が高いことが報告されています。つまり、美味しそうなドリンクの写真や率直な口コミといったUGCが、従来以上に購買意思決定を左右する重要な情報源になっているのです。
飲料という商材はUGCと相性抜群
そして、飲料という商材特性こそUGCと相性抜群です。
食べ物や飲み物の写真はSNS上でもっとも頻繁に見かける投稿の一つではないでしょうか?
美味しいドリンクを飲んだ時、期間限定の新商品を試した時、思わずSNSで友人にシェアした経験のある方も多いはずです。飲食は誰もが日常的に体験する身近なテーマであり、「今日こんな飲み物を飲んだ」「こんな風に楽しんでいる」という共有が自然と行われます。
そのため飲料ブランドはUGCが発生しやすい土壌を持っていると言えます。
また、飲料は味や体験といった感覚的価値が重視される商品です。
しかし実店舗で試飲できないネット通販やD2Cでは、ユーザーは「本当に美味しいの?」「どんな風に楽しめるの?」と不安を感じることがあります。そのギャップを埋めるのがUGCです。実際に商品を飲んだ消費者の感想や写真を見れば、自分の生活に取り入れるイメージが湧き、不安が払拭されます。他の消費者のリアルな声が安心感につながり、購買を後押しする──この点でUGCは飲料マーケティングの強力な味方と言えるでしょう。
総じて、SNSマーケティング全盛の今、UGCは「第三者からのお墨付き」としてブランドへの信頼感や親近感を生み出す重要な役割を果たしています。飲料業界でもUGCを戦略的に活用することで、新商品の話題化からファンコミュニティ醸成、ひいては売上向上まで期待できるため、大きな注目が集まっているのです。
UGCを生む飲料ブランドの成功事例
では実際に、UGCを上手に生み出している飲料ブランドにはどのような例があるのでしょうか。ここではスターバックス、ヤッホーブルーイング、そして株式会社SEAMが手掛ける低アルコールクラフトカクテル「koyoi」の事例を紹介します。それぞれの取り組みから、UGC創出のヒントを探ってみましょう。
スターバックス:体験価値が生む爆発的UGC

スターバックスコーヒーは広告費をそれほどかけずともSNSで高い話題性を維持するブランドとして有名です。
その背景には、顧客体験(UX)への投資とコミュニティづくりがあります。
創業者ハワード・シュルツ氏の言葉に「我々はコーヒーそのものではなく、人間を通じてコーヒー体験を提供している」という趣旨のものがありますが、まさにスタッフの接客や居心地の良い店舗環境づくりに注力することで、ユーザーが「また行きたい」「誰かに共有したい」と感じる場を提供しているのです。
例えばスターバックスでは、バリスタがカップに手書きメッセージを書いてくれたり、新作フラペチーノを試飲させてくれたりといった心温まるエピソードがSNS上で頻繁に語られます。
こうしたポジティブな体験がユーザーによって投稿(UGC)され拡散し、結果的に広告以上の宣伝効果を生んでいます。「スターバックスで○○していたらこんな嬉しいことがあった!」という投稿を目にしたことがある方も多いでしょう。
さらに、スタバはSNS映えする商品や季節限定イベントを次々と展開し、ユーザーの創作意欲をかき立てています。
色鮮やかな新作ドリンクやおしゃれな期間限定タンブラーなどは、思わず写真に撮って共有したくなるものです。
事実、スターバックスジャパンが実施した「#sendyourthanks」キャンペーンでは、同社のチルドカップ飲料を写真に撮ってハッシュタグ投稿すると特典が当たる仕組みでしたが、スタイリッシュなパッケージデザインも相まってInstagram・Twitter上に多数の投稿が集まり成功しています。
このようにスターバックスは製品自体の魅力と顧客体験の質を高めることで、ユーザーが自発的に発信したくなる状況を作り出しているのです。
スターバックス事例から学べるポイントは、「UGCはお金で買うのではなく、顧客体験を向上させた結果として生まれる」ということです。
ユーザーにつぶやいてもらうために予算を使うのではなく、つぶやきたくなる仕組みに予算を使うべきだと指摘されています。つまり企業側は、ファンが自発的にシェアしたくなるような体験価値やコミュニティを提供することに注力すべきなのです。
ヤッホーブルーイング:熱狂的なコミュニティでファンと一緒に拡散させる
近年台頭しているクラフトビールやクラフト飲料ブランドも、UGCを巧みに活用しています。

例えば日本のクラフトビールメーカーであるヤッホーブルーイング(「よなよなエール」などで有名)は、ファンとの積極的な交流によるコミュニティ戦略を行っています。
オウンドメディアやSNS上でユーザーと対話し、時にはビール好きが集まるリアルイベントを開催することで、熱狂的なコミュニティを育成しています。このようにして生まれたコアファンたちが日常的に同社製品の感想や楽しみ方をSNS投稿し、ブランドの知名度向上に寄与しています。
飲料のように味わってみないと分からない商品では、UGCが他の消費者の体験を疑似的に伝える役割を果たし、購入後押しに直結している好例です。
このような事例から学べるのは、ファンとの双方向コミュニケーションとユーザー視点に立ったコンテンツ作りです。リアルなファンの声を積極的に収集・活用し、それをさらに新規顧客への信頼獲得に繋げる好循環を作っています。単に商品を売るのではなく、ユーザーと共にブランド体験を作り上げていく姿勢が、多くのUGCを生む秘訣と言えるでしょう。
低アルコールカクテル「koyoi」のUGC共創戦略(株式会社SEAM)

自社ブランド「koyoi」は、低アルコールクラフトカクテルのD2Cです。
koyoiのマーケティングは、最初からユーザーとの「共創」に重きを置いてまいりました。
具体的には、ターゲット層を集めたデジタル上のユーザーコミュニティを形成し、そこから得られるリアルなニーズを商品開発にフィードバックしています。いわゆるN=1マーケティング(特定の顧客像に徹底的に寄り添った商品開発)を志向し、試作段階からユーザーの声を取り入れることで、発売前からファンを巻き込んでいるのです
このようにユーザーをパートナーとして迎え入れるマーケティングは、ファンのロイヤルティを飛躍的に高めるとともに、そのファン自らが広報担当のようにブランドの魅力を語ってくれる好循環を生み出します。
単に出来上がった商品に対する口コミを待つのではなく、商品ができるプロセスからユーザーを巻き込むことで、発売の瞬間から多くの共感や応援の声(UGC)が飛び交う状態を作り出しています。
UGCを生み出すには?ユーザー心理の理解がカギ
UGC成功事例に共通するのは、ユーザーが「自発的に発信したくなる」仕掛けが上手に組み込まれている点です。
では、人はなぜUGCを投稿したくなるのでしょうか?
ここではユーザー心理の観点からその動機を紐解き、飲料ブランドが活用すべき心理トリガーについて考えてみます。
なぜ人はUGCを自発的に投稿したくなるのか
ユーザーがUGCを投稿する動機には、いくつもの本能的・心理的欲求が関係しています。代表的なものを挙げてみましょう。
- 社会的証明
人は他者の行動を手がかりに自分の行動を決める傾向があります。
他の人がある飲み物を美味しいとSNSで絶賛していれば、「自分も試してみよう」「自分も投稿して仲間入りしよう」と思いやすくなります。
逆に自分が先に投稿することで「この商品は人気なんだ」と他者への社会的証明を与える一員になれる、という心理も働きます。 - 承認欲求・自己表現
SNSは自己表現の場です。美味しいドリンクを飲んだらその喜びを共有し、「いいね!」やコメントといった反応をもらいたいという承認欲求が生まれます。
特にZ世代はSNS上で自分のセンスや価値観を発信することに慣れており、お気に入りのカフェドリンクやおしゃれなボトル飲料の写真投稿は自分らしさのアピールでもあります。
また、自身の発信がきっかけでフォロワーとの会話が生まれたり、場合によってはブランド公式に紹介されることへの期待も投稿意欲につながります。 - 共感・つながり欲求
人は楽しい体験や感動したことがあると、それを誰かと共有したくなります。
美味しいものを「美味しい!」と言い合うことで喜びが増すように、SNSでも「このジュース、本当にリラックスできる味!」「このビール、地元の誇り!」と投稿し、同じ気持ちの人から反応をもらうことで共感による満足感を得られます。
また特定のブランドの愛好者同士でコメントを交わすうちにコミュニティが生まれ、「仲間ができた」という帰属意識が高まることも人を投稿へ駆り立てる要因です。 - 新奇性・話題提供
新発売の商品やユニークなフレーバーに出会うと、「まだ誰も知らないかも?自分が紹介しよう」といった好奇心と優越感が刺激されます。
トレンドに敏感な人ほど、新しい飲料を試してSNSでいち早くレポートすることに熱心です。
こうした流行の最先端に加わりたい欲求や、人に役立つ情報を提供したい気持ちも投稿の原動力になります。 - 利他的動機
自分が「これは良い!」と感じた商品は、友人知人にも薦めたくなるものです。
SNS投稿は不特定多数への発信ではありますが、「同じ悩みを持つ人の参考になれば」という思いで口コミを書くケースもあります。
例えば「このプロテインドリンク、美味しいし栄養たっぷりでおすすめ!」といった投稿は、フォロワーの健康志向の友達を思い浮かべて発信しているかもしれません。誰かの役に立ちたい、喜んでほしいという利他的な感情もUGCを生む大切な要素です。
以上のように、人がUGCを投稿したくなる理由は一つではなく、複数の心理欲求が絡み合っています。
飲料ブランドとしては、これらのモチベーションが高まる環境を用意してあげることで、ユーザーの自発的な発信を促すことができるのです。
飲料ブランドが意図的にUGCを生み出すための施策6選
ユーザーの投稿意欲を引き出すために、飲料ブランド側が意識して仕掛けたい心理トリガーをいくつか紹介します。
①「SNS映え」するビジュアル提供
視覚的な魅力は最も手軽なトリガーです。
パッケージデザインやドリンクそのものの見た目がフォトジェニックであれば、ユーザーは思わず写真に撮りたくなります。スターバックスの季節限定フラペチーノや、クラフトコーラのおしゃれなボトルがSNSで多く拡散されるのはこのためです。
カラフルな色合い、ユニークな形状、映えるロゴなど、見ただけで「シェアしたい!」と思わせる演出を心がけましょう。
②限定感・レア感の演出
人は限定品や期間限定商品に弱く、手に入れると誰かに自慢したくなります。「今しか飲めない○○フレーバー」や「数量限定デザインボトル」などの企画は、ユーザーに希少価値を感じさせ、購入と同時に投稿意欲をかき立てます。
実際、「#期間限定」「#○○先行体験」といったタグとともに飲料を紹介するUGCは多く見られます。
限定商品を手に入れたユーザーが優越感と喜びから自主的に拡散してくれる効果を狙いましょう。
③ユーザー参加型キャンペーン・コンテスト
ハッシュタグキャンペーンやフォトコンテストは古典的ですが有効な手段です。ただし、単に「投稿したら抽選で景品」では一過性で終わりがちなので、お題設定や仕掛けに工夫が必要です。例えば「#私の朝の相棒ドリンク」といったテーマで日常の一コマを募集したり、ユニークな飲み方アレンジを競ったりすると、ユーザー同士が投稿を見て盛り上がれる場が生まれます。投稿自体に参加する楽しさを感じてもらうことが重要です。スターバックスの#sendyourthanksも、感謝の気持ちを伝えるというストーリー性がお題にあったため多くの共感を呼びました。
④共感できるブランドストーリーの発信
企業側のメッセージや世界観がユーザーの価値観と響き合えば、ユーザーはそのストーリーの伝道者になってくれます。例えば「環境に優しいサステナブル素材のボトルを採用」「売上の一部を地域支援に寄付」といった社会的意義のある取り組みは、それに共感したファンによって積極的に語られます。また「このドリンクにはこんな想いが込められています」という開発ストーリーを共有すれば、共感したユーザーが自分の言葉でその想いを拡散してくれるでしょう。単なる商品の機能説明ではなく、人の心を動かす物語を伝えることがポイントです。
⑤公式とのエンゲージメント(リアクション)
ユーザーは自分の投稿にブランド公式アカウントからリアクションがあると大いに喜び、ロイヤルティが高まります。公式がUGCをリポスト(再共有)したり、「いいね」やコメントで反応したりすることで、他のユーザーにも「このブランドはファンの声をちゃんと見てくれている」という印象を与えます。結果としてさらに投稿が増える好循環が生まれます。飲料ブランドでも、自社ハッシュタグの投稿を定期的に紹介したり、優れたUGC投稿者を「アンバサダー」として表彰するなど、ファンとの双方向の交流を演出しましょう。「ブランドと一緒に盛り上がっている」という実感がユーザー側に芽生えれば、自発的な発信は格段に増えていきます。
⑥共創体験の提供
先述のkoyoiのように、商品開発やイベントにユーザーが参加できる仕組みを提供すると、参加者は自分事として積極的に情報発信してくれます。試飲会やファンミーティングで直接ユーザーの声を聞き、それをもとに改良を加えた場合には「自分たちの意見が反映された!」という達成感からUGCが生まれやすくなります。あるいはユーザー投票で新フレーバーを決めるような企画も良いでしょう。自らブランドの一部を形作ったという体験は何物にも代え難く、その誇りを誰かに話したくなるものです。
以上のような心理トリガーを活用し、ユーザーが思わず投稿したくなる接点をデザインすることがUGC創出には欠かせません。ポイントは、ユーザー視点に立って「どうすれば楽しくシェアしたくなるか」を考えることです。企業側の一方的な盛り上げ施策ではなく、ユーザーの内なる動機をそっと後押しするような仕掛けこそが効果を発揮します。
これらを体系的に取り入れたUGC戦略は、ブランドへの信頼感を高め、長期的なファン層を形成する礎となります。
まとめ:UGCを活用してブランド認知度と売上を拡大しよう
現代のマーケティングにおいて、ユーザー生成コンテンツ(UGC)は単なる口コミ以上の価値を持ち、消費者のリアルな声を通じて広告以上の信頼性を提供します。特にZ世代やミレニアル世代にとって、SNSを通じたUGCは購買行動を決定づける大きな要素です。
本記事では、UGC促進のためのユーザー心理の理解から、具体的な実践アプローチ、そして成功事例までを詳しく解説してきました。
- 信頼性の高い発信源として広告以上に効果的
- ストーリー性や体験型プロモーションがUGC創出の鍵
- 限定性・希少性によるFOMOの刺激でシェアを後押し
- SNSで話題化する仕掛けとインフルエンサー活用で拡散力を強化
- ユーザー参加型の共創プロセスでファンコミュニティを育成
UGCは一度発生すれば終わりではなく、継続的にブランドの価値を高める“資産”になります。本記事で紹介した戦略や手法を活用し、UGCを通じてブランド認知度と売上の拡大を実現してみてください。
SEAMが展開するブランド「koyoi」は、WEB広告を一切使用せず、PRと口コミだけでユーザー数を増やした実績を持つ飲料ブランドです。こうしたマーケティングを通じて培った実践的なノウハウを活かし、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を自然と生む飲料商品企画・開発支援サービスを提供しています。
- 「SNSでシェアされる商品を作りたいが、どんなコンセプトにすべきかわからない」
- 「Z世代やミレニアル世代のインサイトを深掘りし、自然と口コミが広がる商品を作りたい」
- 「開発からクリエイティブ制作、プロモーション設計まで、一貫した支援が欲しい」
こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。