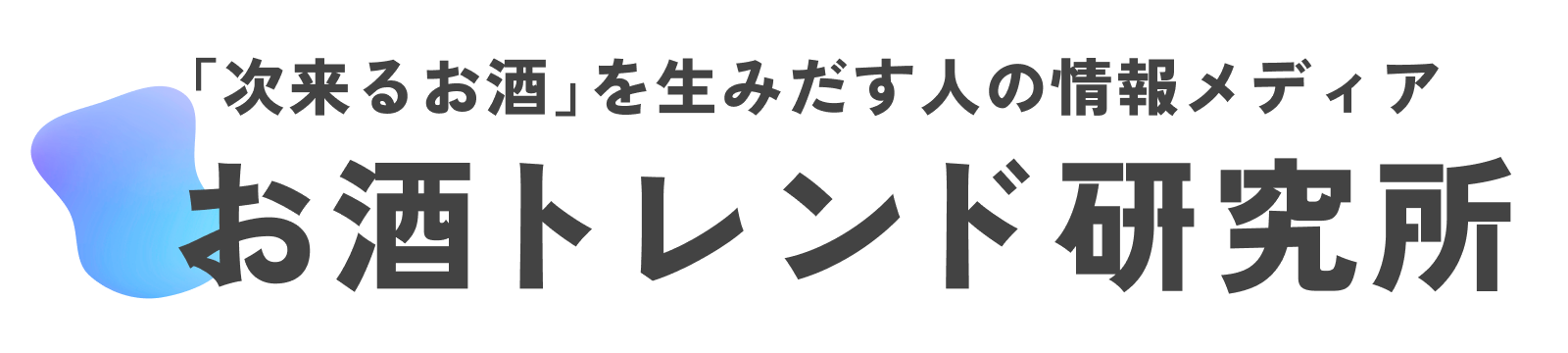D2Cとは?成功事例から学ぶお酒×D2C成功のポイント
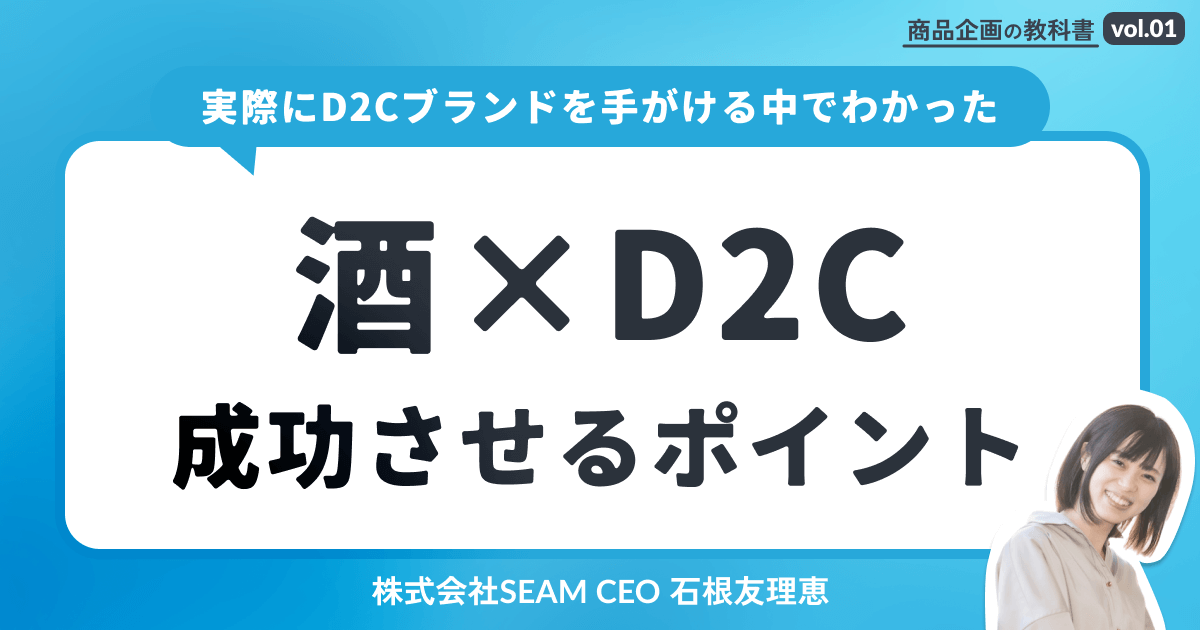
お酒業界において、「どのようにしてZ世代や若年層に響く商品を作ればいいのか?」や「オンラインチャネルを活用してブランドの世界観をどのように伝えるべきか?」と悩むことはありませんか?
従来の大量生産・大量販売型の流通モデルでは、個別ニーズに応じた柔軟な商品開発や、消費者との深い関係構築は難しいものです。ところが、2025年現在、注目を集めているのが 「D2C(Direct to Consumer)」モデル です。
D2Cモデルは、ブランドが中間業者を介さずに直接消費者とつながることで、パーソナライズされた商品提案やブランド世界観を反映したマーケティングを可能にします。特に、Z世代を中心とした若年層は体験型消費やストーリー性のある商品を重視するため、お酒業界との親和性が非常に高いのが特長です。
本記事では、弊社SEAMが実践してきた若年層向け商品のプロデュース経験をもとに、以下の内容を解説します。
- お酒業界におけるD2Cの可能性
- お酒D2C市場の現状と成長要因
- D2Cモデルで成功するためのポイント
- 法規制とD2C展開で注意すべきポイント
- D2Cを活用した今後のブランド戦略の展望
「若年層に響くお酒商品の開発に挑戦したい方」「D2Cモデルを活用したブランド戦略を検討している方」「オンラインを活用した新しい飲酒体験を提供したい方」はぜひ最後まで読んでみてください!
はじめに|お酒業界におけるD2Cの可能性とは?
お酒業界におけるD2Cの導入は、消費者に直接アプローチできるというユニークな利点を提供します。
このモデルは、消費者の個別ニーズに応えることができ、迅速な市場適応を促進します。特にZ世代の若年層は、ブランドの世界観を重視し、個々にパーソナライズされた体験を求める傾向が強いため、D2Cとの親和性が高いとされています。これにより、従来の「モノ消費」から「コト消費」へのシフトが進み、お酒を単なる商品ではなく、体験として楽しむ新たな文化が形成されています。D2Cはこうした変化を促進し、お酒業界に新たな価値をもたらす可能性を秘めています。
D2Cの定義
D2C(Direct to Consumer)とは、メーカーやブランドが中間業者を介さずに直接消費者に商品を販売するビジネスモデルを指します。
このモデルの主な特徴としては、以下の3点が挙げられます。
- 顧客データを自社で保有・分析できる。
- ブランディングやマーケティングにおける自由度が高い。ブランドが独自のアイデンティティを築くための手段としても非常に有効。
- 顧客データも活用して、顧客とのダイレクトなコミュニケーションを図ることができる。
従来型の販売モデルとの違いは以下のように整理することができます。
D2Cモデルを採用するメリットは、❶顧客データの活用、❷ブランディングの自由度、❸ダイレクトで自由なマーケティング施策にあります。
| 従来型の販売モデル | D2Cモデル | |
|---|---|---|
| 流通ルート | メーカー → 卸業者 → 小売店 → 消費者 | メーカー → 消費者 |
| 顧客データの活用 | 小売店が主にデータを所有し、メーカーは直接データを得にくいため、商品改善に時間がかかる。 | メーカーが直接データを収集し、消費者の嗜好を分析・迅速な改善が可能。 |
| ブランディング | 流通業者や小売店の影響が大きく、ブランド戦略の自由度が低い | ブランドの世界観を自由に表現しやすい |
| マーケティング戦略 | 小売店を介するため、消費者との直接的な対話が少ない | SNSやオンラインイベントを活用し、ダイレクトなマーケティングが可能 |
お酒D2C市場が拡大する背景
お酒D2C市場の急成長は、一過性のトレンドではなく、消費者の価値観や購買行動の変化に根ざした構造的なシフトによるものです。とりわけ、若年層の消費者は「お酒をただ買う」のではなく、「自分のライフスタイルや価値観に合ったブランドを選び、それを楽しむ」という視点を持っています。これにより、従来の大量生産・大量販売のモデルでは捉えきれなかったニーズに対応できるD2Cブランドが勢いを増しているのです。
D2C市場の成長を支える要因は複数ありますが、特に影響が大きいのは以下の3つです。
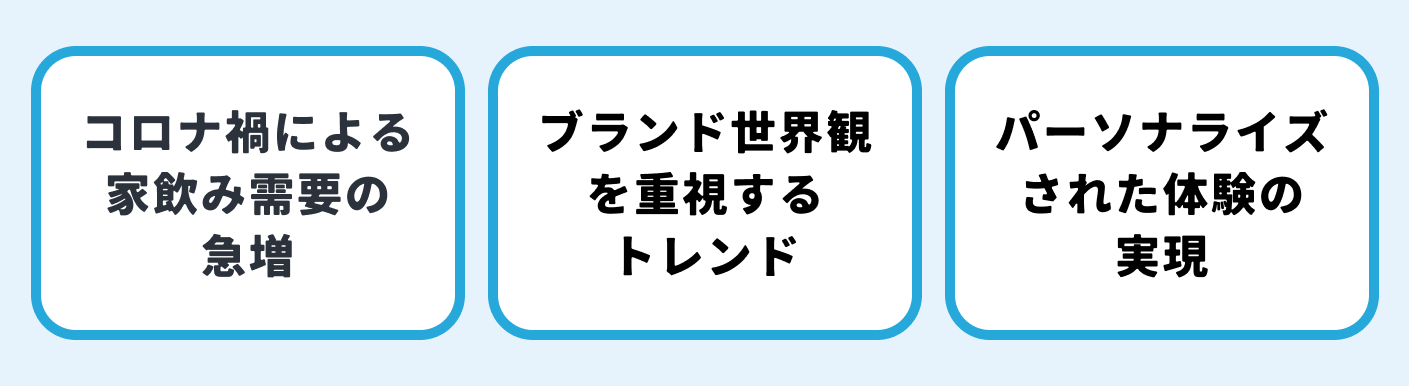
1. コロナ禍による家飲み需要の急増
2020年以降、新型コロナウイルスの影響で飲食店での飲酒が制限され、自宅での飲酒、いわゆる「家飲み」が定着しました。それに伴い、消費者はスーパーやコンビニで手に入るお酒だけでなく、「自分に合った特別な一杯」を求めるようになりました。
従来の流通では手に入らない個性的なクラフト酒や、自分の嗜好に合わせて選べるサブスクリプション型のサービスは、こうした消費者の変化にフィットし、お酒D2C市場の成長を加速させました。特にECを活用したお酒の販売は、この流れに乗って一気に拡大し、消費者の間でも「お酒はオンラインで買う」という新しい習慣が根付いてきています。
2. ブランドのストーリーテリングやビジュアル重視の潮流
現代の消費者、とりわけZ世代やミレニアル世代は、商品の品質だけでなく、「そのブランドがどのような背景やストーリーを持ち、どんな価値観を大切にしているか」に強く共感します。お酒も例外ではなく、D2Cブランドはこれを巧みに活用しています。
例えば、環境に配慮したサステナブルな製法や、地元の農家と協力した原材料の選定、あるいは特定のカルチャーを反映したパッケージデザインなど、ブランドの個性を前面に出すことで、消費者の共感を呼び、ファンを獲得する戦略が功を奏しています。
また、SNSを活用したブランディングも重要な要素です。InstagramやTikTokでは、単なる商品紹介ではなく、「このお酒を飲むことでどんな体験ができるか?」というライフスタイル提案が共感を呼び、口コミを通じて自然と広がっていきます。
3. デジタルテクノロジーの進化によるパーソナライズされた体験
D2Cの強みは、消費者データを直接取得し、それをもとにしたマーケティングや商品開発が可能な点にあります。従来の小売流通では、消費者の具体的な嗜好や購入履歴を把握することが難しかったのですが、D2CではECサイトやSNSを通じて顧客の行動データを分析し、それを活用できます。
特に、お酒という商材は人によって好みが様々です。だからこそ、「辛口が好きな人には新作の辛口日本酒をおすすめする」「過去にフルーツ系のカクテルを購入した人には、次の季節にぴったりのフレーバーを提案する」といった、一人ひとりに寄り添ったマーケティングが必要になります。こうしたパーソナライズされた体験は、消費者の満足度を高め、リピート率の向上にもつながります。
今後も酒類D2C市場はさらに拡大し、多様な顧客ニーズに応える柔軟性と創造性が求められるでしょう。
海外・国内の成功事例紹介
海外・国内の酒類D2Cの成功事例をご紹介します。
Haus(アメリカ)

健康志向のミレニアル世代をターゲットに、天然素材を使用した低アルコール飲料を提供しているアメリカ発のブランドです。ミニマルで洗練されたボトルデザインと、ヘルシーなライフスタイルを提案するブランドイメージが特徴。
彼らのブランドイメージにあわせた、洗練されたECサイトのデザインによって一貫したブランド体験を生み出しています。
Empirical Spirits(デンマーク)

EMPIRICALは、伝統的な蒸留技術と先進的なフレーバー技術を組み合わせた独自のクラフトスピリッツを展開しているデンマークのブランドです。ボトルデザインやブランドイメージは、シンプルでありながら洗練されており、彼らの革新的なスピリッツを象徴しています。自社のECサイトにおいても、自社に関するストーリーを伝えるジャーナルなどを通してよる深くターゲットとの関係を築き、ブランドの世界観をより深く伝えています。
koyoi(日本)

koyoi(コヨイ)は、日本の低アルコールのクラフトカクテルを提供するD2Cブランドです。アルコール度数3%と、お酒が弱い人でも楽しめるように設計されています。
本格的な味わいを追求し、ナチュラル製法にこだわっており、「無理なく楽しめるものをお届けしたい」というコンセプトのもと、心地よい時間を過ごせるような商品を提供しています。WEBサイトでは、パーソナライズ診断などを通じて顧客のニーズに合わせた提案を行っています。
WAKAZE(日本)

世界でSAKEが造られ飲まれる世界の実現を目指し、ルールにとらわれないSAKEを造っているブランドです。日本の三軒茶屋とフランスパリ、そしてアメリカにも拠点があり、オンラインストアなどのD2Cも含めて多角的な展開をしています。
お酒D2C成功のカギとなるポイント
お酒D2C市場で成功するためには、以下の3つの要素が重要となります。
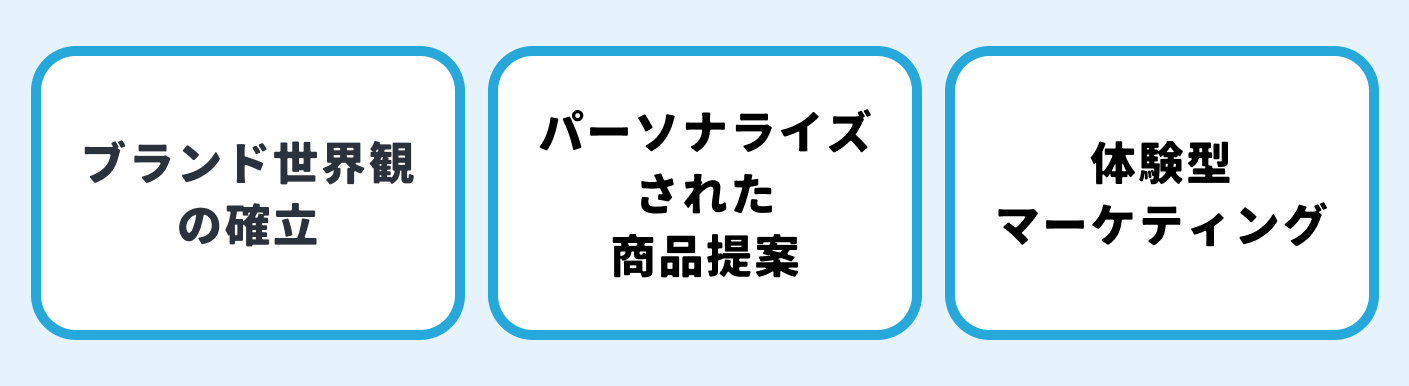
それぞれについて詳しく説明します。
ブランド世界観の確立|共感を生むビジュアルとストーリーテリング
「なぜこのブランドを選ぶのか?」— これは、D2Cブランドが消費者に対して明確に示すべき問いです。お酒は単なる飲み物ではなく、その背景にあるストーリーや価値観、世界観に共感した人が選ぶものになっています。
成功しているお酒D2Cブランドは、単に「美味しいお酒」ではなく、「このブランドと一緒に時間を過ごしたい」と思わせるような世界観を構築しています。例えば、ミニマルで洗練されたデザインを取り入れ、SNSでのシェアを促すブランドもあれば、地域の特産品を活かし、クラフト感や地元愛を感じられるストーリーを打ち出すブランドもあります。
また、ブランディングの一貫性も重要です。
パッケージデザイン、SNS投稿、ECサイトのデザイン、すべてが統一された世界観のもとに作られていると、ブランドの個性がより鮮明になります。たとえば、Z世代の間で人気のD2Cワインブランドは、エコ素材のボトルを採用し、そのビジュアルも環境意識の高いシンプルなデザインに統一。さらに、SNSで「持続可能なワイン文化」を発信することで、価値観に共感する消費者の支持を集めています。
- 視覚的な一貫性:パッケージ、ウェブサイト、SNSで統一感のあるデザインを展開
- ストーリーテリング:商品開発の背景やブランドの哲学を丁寧に伝える
- 社会的メッセージ:サステナビリティや地域貢献など、価値観に共感を呼ぶ要素を持つ
パーソナライズされた商品提案|データ活用による顧客体験向上
今の消費者は、画一的な商品ではなく、「自分に合ったもの」を求めています。お酒D2Cでは、この「パーソナライズドな提案」が競争力の決め手になります。
例えば、AIを活用して消費者の好みに合ったお酒を提案するサービスが増えています。「普段はフルーティーなカクテルを好む人には、季節限定のフルーツリキュールをおすすめ」「辛口の日本酒を好む人には、特定の蔵元の限定酒を紹介」など、一人ひとりの好みに応じたレコメンドを行うことで、満足度を高め、リピーターを増やしています。
また、定期購入サービス(サブスクリプションモデル)も効果的です。「あなたにぴったりのお酒が毎月届く」といった体験は、新しい味との出会いを提供し、飽きさせない工夫として機能します。実際に、ある日本酒D2Cブランドは「味わい診断」を実施し、ユーザーの嗜好に合わせた日本酒をセレクト。これが話題となり、サブスク会員が急増しました。
- サブスクリプションモデル:好みに合わせたお酒を毎月お届けし、新たな発見を提供
- AI・データ活用:購入履歴やレビューを分析し、次に試すべき商品を提案
- ギフト提案:贈る相手の嗜好やシーンに応じた商品をレコメンドし、パーソナライズ感を演出
体験型マーケティング|サブスクリプションやテイスティングイベント
Z世代を中心に、「モノ消費」よりも「コト消費」を重視する傾向が強まっています。つまり、「どんなお酒か」よりも、「そのお酒を通じてどんな体験ができるか」が、購入の決め手になっています。
これをうまく活用しているのが、テイスティングイベントや、飲み方のシーン提案を行うブランドです。例えば、オンラインでソムリエや酒蔵の職人と直接話しながらテイスティングを楽しめるイベントは、D2Cならではの強みを生かした施策のひとつ。消費者がただ「買う」だけでなく、「体験する」ことで、ブランドへの愛着が深まります。
また、オフラインイベントでは、ポップアップストアで特別なペアリング体験を提供することで、商品を試す場を作り、ファンを増やしています。例えば、クラフトカクテルD2Cブランドが開催した「ナイトカフェイベント」では、DJが流す音楽とともに、限定のオリジナルカクテルを提供。お酒を単なる「飲み物」ではなく、「カルチャーとしての体験」に変えたことで、若年層のファン層を拡大しました。
- サブスクリプションの活用:定期的に異なるフレーバーを届け、体験を継続
- オンライン・オフラインイベント:ブランド担当者との交流や、限定商品を試せる場を提供
- シーン提案型プロモーション:「夜のリラックスタイムにぴったり」「週末の家飲みをもっと楽しく」といった具体的なシーンで訴求
法規制とD2C:酒類販売で注意すべきポイント
お酒のD2Cビジネスを成功させるためには、法規制への理解と対応が欠かせません。
特に酒税法や年齢確認に関するルールは厳格に定められており、これらを遵守しながらビジネスを展開することが、ブランドの信頼性向上にもつながります。ここでは、通販での販売時に気をつけるべきポイントや、日本と海外の法規制の違い、D2Cブランドが法規制を乗り越えるための戦略について詳しく解説します。
通販における酒税法・年齢確認の課題
まず、日本国内で酒類を販売する際には、適切な販売免許を取得する必要があります。
たとえば、「通信販売酒類小売業免許」など、販売形態に応じた免許が求められます。これを怠ると法的なリスクが発生するため、事業を始める前に必ず確認が必要です。
また、未成年者飲酒防止の観点から、オンライン販売では年齢確認のプロセスを徹底することが求められます。
ECサイトでの会員登録時に生年月日の入力を必須にしたり、初回購入時に運転免許証やマイナンバーカードによる本人確認を実施したりするのが一般的です。さらに、配送時に宅配業者が対面で年齢確認を行う仕組みを導入することで、より確実な対策を講じることができます。
その一方で、年齢確認のプロセスが煩雑すぎると、消費者の購入意欲を損ねる可能性もあります。
そのため、デジタルID認証などの最新技術を活用し、スムーズかつ確実に年齢確認を行う仕組みを構築することが理想的です。
各国の法規制の違いと日本特有の課題
酒類販売に関する法規制は国や地域によって大きく異なります。特に海外進出を検討しているブランドは各国の法規制の違いを押さえることが重要です。
- アメリカ
- 州ごとに異なるルールが適用されており、一部の州ではD2Cによる酒類販売が禁止されているケースもあります。
- 販売が許可されている州でも、配送時の本人確認が義務付けられるなど、厳格な管理が求められます。
- ヨーロッパ
- EU圏内で共通する規制がある一方で、広告やプロモーションに関するルールは国ごとに異なります。
- たとえば、イギリスやドイツでは、未成年向けと見なされるデザインやマーケティング手法が禁止されており、慎重な対応が必要です。
- アジア
- 韓国ではオンラインでの酒類販売が原則禁止されている
- 中国では輸入酒類の販売に関する認証手続きや関税対応が複雑で、越境ECのハードルが高い
- 日本国内
- 過度な飲酒を助長する広告表現が禁止されているほか、地域ごとに独自の酒類販売規制が存在する場合があります。
- たとえば、健康効果を暗示するような表現や、「飲みやすさ」を過度に強調する表現は規制の対象となるため、マーケティングの際には細心の注意が必要です。
以上のように、日本では当然のルールやサービスも他国では異なることもあるため、海外市場に商品を投入する前に慎重なリサーチ・検討が必要です。
D2Cブランドが法規制を乗り越えるために
法規制は事業の障壁になることもありますが、ブランド戦略に組み込むことで、むしろ競争優位性を築く要素にもなり得ます。たとえば、年齢確認のプロセスを単なる義務ではなく、消費者にとって「安心して購入できる仕組み」としてアピールすることで、ブランドの信頼性を高めることができます。
このように、法規制を単なる障害と考えるのではなく、ブランドの信頼性を高めるための要素として捉えることで、お酒D2Cブランドの成功につなげることができます。
まとめ:お酒D2Cが切り拓く未来の飲酒体験
近年、消費者の嗜好や購買行動の多様化に伴い、お酒業界においてもD2C(Direct to Consumer)モデルへの注目が高まっています。D2Cは、消費者とブランドが直接つながることで、個々のニーズに合わせた商品提案やパーソナライズドな体験を提供できるビジネスモデルです。特にZ世代を中心とした若年層は、ブランドの世界観や体験型消費を重視するため、D2Cとの親和性が非常に高いといえます。
本記事では、お酒D2C市場の現状や成長要因、成功するためのポイント、さらには法規制への対応について詳しく解説しました。
- ブランド世界観の確立 共感を呼ぶストーリーテリングと統一感のあるビジュアルデザイン。
- パーソナライズされた商品提案 データ活用により顧客一人ひとりに合わせた体験を提供。
- 体験型マーケティング サブスクリプションやオンラインテイスティングイベントを通じた体験価値の提供。
お酒D2C市場は、単なる商品販売から「体験を提供するブランド」への進化が求められています。ここで紹介したポイントや市場予測を参考に、D2Cモデルを活用した新たな飲酒文化の創出に取り組んでみてください。消費者一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、パーソナライズされた体験を提供することで、これまでにない革新的な飲酒体験を生み出すブランドへと成長していきましょう。
株式会社SEAMでは、自社の20〜30代向け低アルコールカクテル商品開発で培った実践的なノウハウ をもとに、飲料商品プロデュース支援サービスを提供しています。
SEAMの強みは、単なるコンセプト設計にとどまらず、開発・デザイン・プロモーションまで一貫して伴走できる点です。特に、Z世代を中心とした若年層コミュニティとの共創経験や、パーソナライズドな商品提案ノウハウを活かし、消費者に響く商品の開発とブランド体験の提供を支援します。
- どんな商品コンセプトにすべきかわからない
- ターゲットのインサイトを深掘りし、消費者に響く商品を作りたい
- 開発からプロモーションまで、一貫したサポートが欲しい
SEAMでは、こうした課題をワンストップで解決します。お問い合わせはお気軽にどうぞ!