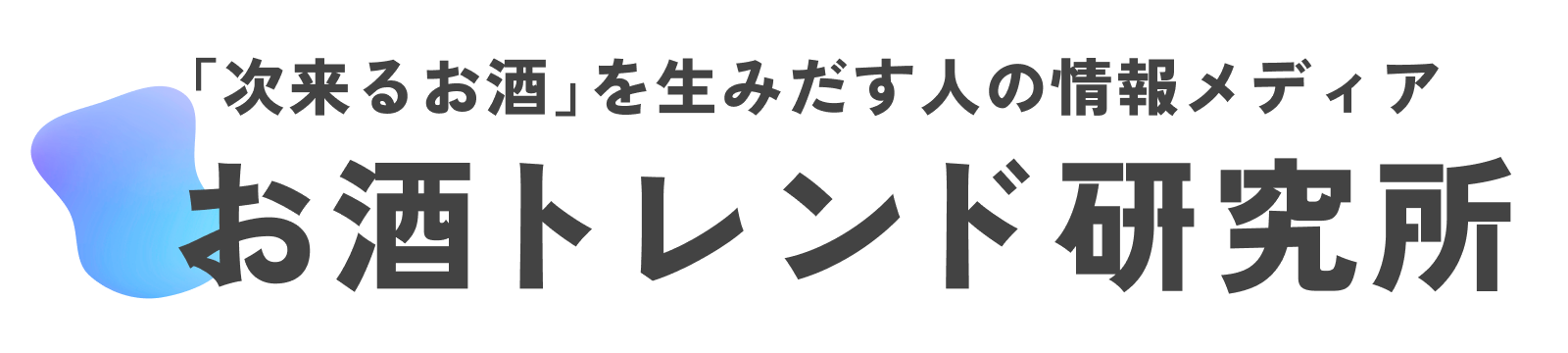商品開発のためのデプスインタビュー実践ガイド|「なぜ?」を深掘りして消費者インサイトを発見する
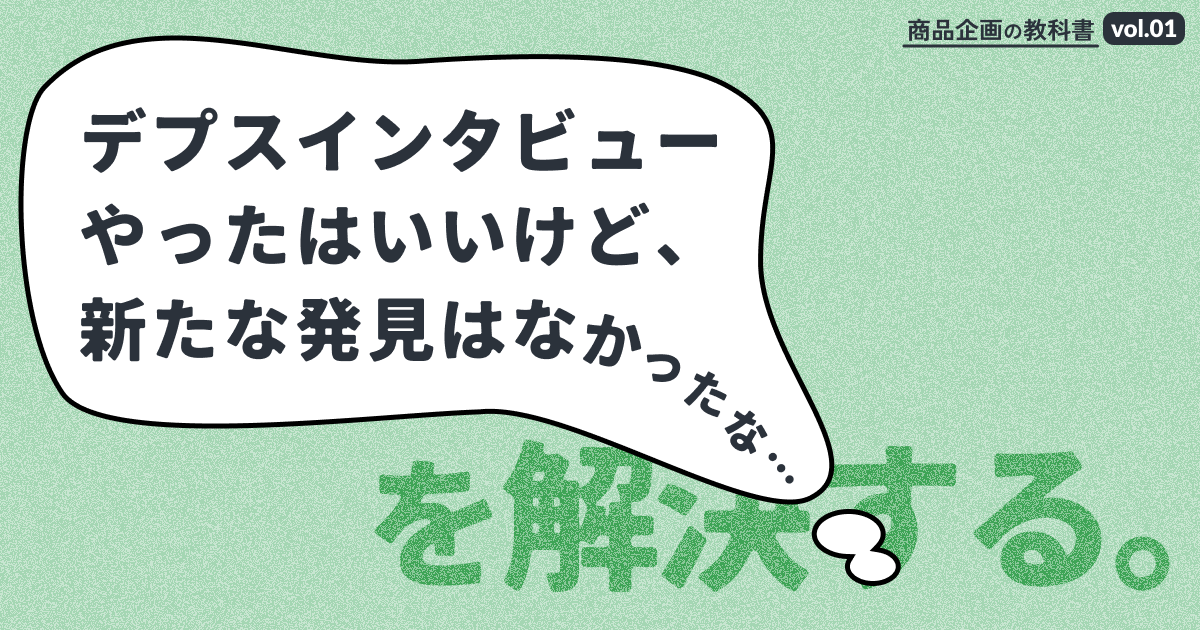
「新商品のアイデアが浮かばない」「顧客調査をしているのに、なぜかヒットに結びつかない」といった悩みはありませんか?定量調査やアンケートでは、消費者が意識している範囲の回答しか得られないため、本当の動機や矛盾、無意識の欲求を見逃してしまう場合があります。
そこで注目したいのが、一人ひとりの行動や感情をじっくりと掘り下げるデプスインタビューです。たった一人の声の深掘りから、思いがけない商品アイデアやマーケティング施策が生まれることもあります。
本記事では、デプスインタビューの概要から、具体的な手法、結果の解釈・活用の方法まで、分かりやすく解説。最後には、今回のポイントを振り返るまとめも用意しています。
- N=1インタビューの重要性とメリット
- 良質なインサイトを得るためのデプスインタビュー手法
- 結果の解釈・活用の仕方
- 新商品企画やマーケティングにどうつなげるかのポイント
「定量データだけでは気づけない、消費者の“リアルな本音”を引き出したい」「デプスインタビューの具体的な進め方や結果分析を知りたい」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
デプスインタビューで「良質なインサイト」を引き出すための前提知識
デプスインタビューのテクニックに入る前に、インサイトという言葉の意味や、他の調査手法との違いを確認しておきましょう。前提知識を押さえておくことで、インタビューの目的や位置づけが明確になり、より質の高い調査設計につながります。
インサイトとは何か?
インサイト(Insight)とは、マーケティングにおける「消費者自身も気がついていない隠れた本音」や「潜在ニーズ」を指します。
簡単に言えば、ユーザーを行動に駆り立てる深層心理や真の動機です。
表面的に観察できる事実(例:「週に3回この商品を購入している」)や、ユーザーが口にする意見(例:「この商品は便利だと思う」)とは異なり、インサイトはユーザーの内面に潜む本当の理由や価値観を指します。
ユーザー自身が自覚していなかったり、言語化できなかったりするため、インサイトの発見には解釈や洞察が必要です。
ある商品のリピーターに対し、「なぜその商品を繰り返し使うのか?」と直接聞いても、本人は明確に答えられないことがあります。「安いから」「みんな使っているから」といった表面的な意見しか出てこない場合、それは本当の動機(インサイト)ではなく建前の回答です。
インサイトとは、そうした建前の裏にある「本当は○○だから使っている」という隠れた理由を指します。インサイトを得ることで、ユーザーの潜在的な欲求や課題を深く理解でき、商品コンセプトの開発やマーケティング戦略において競合優位性を生み出すアイデアにつながります。
良質なインサイト発見になぜデプスインタビューは不可欠か?
良質なインサイトは、数値データをいくら集めても必ずしも見えてくるとは限りません。なぜなら人間の行動は、ロジカルに説明しきれない複雑な要素(矛盾・本能的欲求・周囲の目など)に左右されるためです。
そこで役立つのが、一人の消費者に対して時間をかけて深く掘り下げる「デプスインタビュー」です。
1. 矛盾や感情の揺れを丁寧に拾える
アンケートでは「朝はカフェラテ派です」と答えていても、実際には夜に甘い物を多く摂るから“帳尻合わせ”で朝はカフェラテを選んでいる…といった複雑な心理があるかもしれません。こうした矛盾や感情の揺らぎは、時間をかけて対話を重ねることで初めて見えてくるものです。
2. 深い洞察から普遍化のヒントを得やすい
たった一人の消費者の声でも、そこに潜む動機や価値観は他の人々にも共通している可能性があります。N=1で深く突き止めた要素を軸に、より大きなターゲットに当てはめて検証することで、新しい需要やニーズを発見しやすくなります。
デプスインタビューとグループインタビューの違い
デプスインタビューは1対1で行う個別インタビューであり、グループインタビュー(フォーカスグループ)は複数名の参加者を同時に対象とする座談会形式のインタビューです。それぞれメリット・デメリットがあり、得られる情報の性質も異なります。
デプスインタビューのメリット
- 本音や個人的な経験を語りやすい
- デプスインタビューでは安全でプライベートな環境でじっくり話を聞けるため、参加者は他人の目を気にせず本音や個人的な経験を語りやすいのが利点です。
- 1人あたり最低30分、多くは1~2時間かけて深く質問を重ねることで、表面的な意見の背後にある感情面の背景や潜在ニーズまで掘り下げることができます。
- その結果、複雑な意思決定のプロセスや過去から現在に至る行動の流れを詳細に振り返ってもらい、心境の変化や隠れた動機を引き出すことが可能です。
- デリケートなテーマでも情報を引き出しやすい
- 金融や健康などデリケートなテーマでも、一対一なら他者を気にせず話せるため深い情報を得られます。
グループインタビューのメリット
- 参加者同士の議論や共感で意見が引き出される
- 誰かの発言に他の参加者が刺激を受け「自分もそう思っていた」「そういえば…」と新たな意見が出るなど、グループダイナミクスから多様な視点を短時間で収集できます。
要するに、個々の内面に迫るにはデプスインタビュー、複数の意見の広がりや相互作用を見るにはグループインタビューが適しています。目的に応じて手法を選ぶことが重要ですが、本記事のテーマである「良質なインサイト」を得るという点では、じっくり深掘りできるデプスインタビューが有効な場面が多いでしょう。
インサイトを引き出す「デプスインタビュー」のコツ9選
それでは、デプスインタビューでインサイトを引き出すための具体的なコツを9項目紹介します。調査の準備段階からインタビュー中のテクニック、インタビュアーの心構えまで、実践で役立つポイントを網羅しました。
1. インタビューの目的を「問い」に落とし込む
デプスインタビューを始める前に、調査の目的を明確な問いとして定義することが最重要です。何のためにインタビューを行い、どんなインサイトを得たいのかを曖昧なまま進めてしまうと、質問が場当たり的になり、得られた回答も分析しづらくなります。「ユーザーの購買心理を知りたい」という目的なら、「なぜユーザーは商品Xを選ぶのか?」「商品Xはユーザーのどんな課題を解決しているのか?」といった具体的なリサーチクエスチョンに落とし込みます。目的が複数ある場合は優先順位をつけ、インタビュー終了までに必ず明らかにしたい核心の問いを設定しましょう。
明確な問いが定まれば、質問項目の設計やインタビューフローも組み立てやすくなります。逆にゴールが定まっていないと、質問が散漫になったり重要な論点を聞き逃したりしがちです。インタビュー中も「この問いに答えるには他に何を聞くべきか?」と自問しながら進めることで、ブレずに本質に迫ることができます。目的を問いに落とし込む作業は調査設計の基本ですが、良質なインサイトを得るための羅針盤となる重要なステップです。
2. 相手が本音を語れる関係性を築く(ラポール形成)
インタビューでは、参加者が安心して本音を話せる雰囲気作りが欠かせません。調査の成否は、インタビュアーと参加者の信頼関係にかかっていると言っても過言ではありません。
もっとも大事なのは、「対話相手との間に生まれる信頼関係や心が通い合った関係」を意味します。
短時間でその関係を築くために有効なポイントは、大きく「共通点を見出すこと」と「決して相手を否定しないこと」です。
具体的には、インタビューの冒頭で丁寧に挨拶と自己紹介を行い、場を和ませる簡単な雑談を挟みましょう。参加者の緊張が解けるよう、仕事や趣味、家族構成などからお互いに共感できる話題を探ります。
「自分と共通点がある」と感じると人は心を開きやすくなります。また、参加者の発言に対して否定やジャッジをせず、相槌や共感を示すリアクションを心がけてください。「正解や間違いはないので率直に教えてください」と最初に断っておくのも有効です。インタビューの目的や流れを最初にきちんと説明することも、参加者の不安を和らげ協力を得るうえで大切です。
ラポールが形成されると、参加者は「この人なら本当のことを話しても大丈夫だ」と感じ、建前ではなく本音ベースで語ってくれるようになります。デプスインタビューではまず信頼関係の醸成に時間を割き、その上で本題の質問に入るようにしましょう。
3. 「行動→理由→感情」の順で掘り下げる
インタビューでインサイトを得るには、質問の順序や深掘りの仕方にも工夫が必要です。
特に有効なのが、具体的な行動から始めて、その理由(背景)、さらにそこに伴った感情へと段階的に問いを深めていくアプローチです。
例えば「直近で〇〇を購入したのはいつですか?どんな商品を選びましたか?」といったように、過去の具体的な行動エピソードを引き出します。
「その商品を選んだ理由は何ですか?」と問い、行動の背景にある判断基準や動機を語ってもらいます。
さらに深掘りするため、「そのときどんな気持ちでしたか?」「それはあなたにとってなぜ重要だったのですか?」と感情や価値観に迫る問いを投げかけます。
このように「事実→理由→感情(価値観)」と段階的に聞くことで、いきなり核心を尋ねるよりも自然に深層心理にアプローチできます。
例えば直接「購入の動機は?」と質問すると、参加者は自分でも無自覚な深層心理について答えづらく、結果として建前的な答えになりがちですよね。
しかし「いつ・どこで・何を買ったか」という事実を思い出してもらい、「なぜそれを選んだか」を振り返る中で自身でも理由を再認識し、さらに「そのときどう感じたか」を語るうちに、自分でも気づいていなかった本音(インサイト)が言語化されていきます。
この手法は時間をかけて「5回のwhy?」を繰り返す質問にも通じ、表面的な回答から最終的に本人の価値観や欲求といった根底部分を引き出す効果があります。
インタビューでは、漠然と「どう思いますか?」と聞くより、このような順序立てた深掘りを意識しましょう。一連の流れを踏むことで参加者自身が自己分析し、本音にたどり着く手助けとなります。
4. Yes/Noで終わらない質問を用意する
良質なインサイトを得るためには、質問の形にも注意が必要です。Yes/Noで答えられる閉ざされた質問は極力避け、自由に説明してもらえるオープンな質問を中心に組み立てましょう。
「はい/いいえ」で終わってしまう質問では会話が広がらず、深い情報を引き出すことが難しくなります。
回答が一言で終わらないよう、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうやって)を活用しつつ問いを工夫しましょう。
「この製品は便利だと思いますか?」
→「はい、思います/いいえ、思いません」で終わってしまう。
「この製品のどんなところに便利さを感じますか?」
→具体的なポイントや理由が語られる。
また、回答を深めるための追加の掘り下げ質問も用意しておくと効果的です。
例えば参加者の答えに対してさらに「それはなぜですか?」「もう少し詳しく教えていただけますか?」と促すことで、より具体的で踏み込んだ話を引き出せます。
ただし、このとき注意すべきは質問にこちらの想定する方向性を盛り込まないことです。
たとえば「〇〇だからですか?」と誘導めいた聞き方をすると、本来の相手の視点を歪めてしまう恐れがあります。あくまで中立的なスタンスで、相手の言葉で語ってもらうことを優先しましょう。
オープンクエスチョンを駆使すれば、参加者は自分の言葉で自由に説明できるため、思いもよらない情報や本音が飛び出しやすくなります。質問票を作成する際には、一問一問が閉ざされた質問になっていないか見直し、必要に応じて言い換えておきましょう。
5. 「沈黙」を恐れない
インタビュー中に訪れる沈黙の間は、多くのインタビュアーにとって気まずく感じるものです。つい間を埋めようとして次の質問に飛びたくなりますが、沈黙を恐れず上手に活用することも深掘りのコツです。
実は、参加者が考え込んで黙っている時間には、その場で言葉にされていない何かしらの感情や思考が巡っている可能性があります。
この貴重な内省の時間をインタビュアーが焦って遮ってしまうと、深い洞察の芽を摘んでしまいかねません。
デプスインタビューでは1対1で十分な時間をかけて対話するため、無理に回答を急かさず沈黙の間を大切にする姿勢が求められます。
質問を投げかけた後、相手が考え始めたら焦らずに待ちましょう。
5秒、10秒と沈黙が続くと長く感じますが、相手は記憶をたどったり感じ方を整理したりしているかもしれません。
インタビュアーが落ち着いて待てば、参加者は言葉を選びながらもより深い答えを導き出してくれることがあります。「間が空いても大丈夫」という空気を作るため、自分自身がリラックスし、相手にプレッシャーを与えない穏やかな表情でいることも大切です。
もし相手が答えあぐねている様子なら、「少し考えていただいて大丈夫です」と一言添えて待つのも手です。沈黙の後に語られる内容は、往々にして熟考された本音や新たな視点が含まれています。インタビューでは沈黙も貴重な情報の一部と捉え、恐れずに受け入れましょう。じっくり傾聴する姿勢が、信頼関係をさらに強めることにもつながります。
6. 想定外の答えを歓迎する姿勢をもつ
インサイトを探索する目的でインタビューを行う場合、事前にいくつか仮説や期待する答えを想定していることが多いでしょう。しかし、インタビュー中に自分の想定とは異なる答えや話の方向性が出てきたときこそ、インサイト発見のチャンスです。それを邪魔せず歓迎する姿勢を持つことが重要です。
インタビュアーが陥りがちなミスとして、議論が仮説と違う方向に進み出すと不安になり、元のシナリオに引き戻そうとしてしまうことがあります。
たとえば「本当はこう答えてほしいのに…」という思いから話題を変えたり、無意識に表情に出してしまったりすると、参加者は敏感に感じ取って発言を自己検閲してしまいます。それでは新たな洞察は得られません。
想定外の展開こそインタビューの醍醐味と捉え、面白い方向に話が広がりそうならむしろ深掘りしてみましょう。「なるほど、そういう考えもあるのですね」と肯定し、更に「詳しく聞かせてください」と促せば、予想していなかった真実に行き着くかもしれません。
特にデプスインタビューでは、一人ひとり背景や価値観が異なるため回答のパターンも多様です。仮説にない意見が出たら、「なぜそのように感じたのか?」と掘り下げることで、他の人には共通しないセグメント特有のインサイトが見つかることもあります。また、インタビュー対象者全員が同じ答えになるとは限らないので、少数派の声にも価値があると心得ましょう。多数の人に当てはまるニーズばかりでなく、小数だからこそ競合が見落としているニッチなニーズがインサイトの場合もあります。
重要なのは、インタビュアー自身が先入観にとらわれず柔軟であることです。想定外の答えを排除するのではなく、「そう来たか!」と楽しむくらいの余裕を持って臨みましょう。その姿勢が参加者にも伝われば、より率直で自由な議論が展開し、結果的に質の高いインサイトが得られる可能性が高まります。
7. 発言の裏側にある「前提」や「価値観」を探る
参加者の発言内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、その裏にある前提や価値観に目を向けることもインサイト発掘には欠かせません。
人は自分の考えを語るとき、暗黙の前提(当たり前だと思っていること)や大切にしている価値観を背景に話しています。インタビュアーはそこにアンテナを張り、「なぜこの人はこう考えるのか?」を深堀りする質問を投げかけましょう。
これはまさに「それはあなたにとってなぜ重要なのですか?」と問うラダリング的な深掘りであり、表明された意見の背後にある信念体系を炙り出す狙いがあります。
参加者「値段が一番大事だから、常に一番安い商品を買います」
あなた(表面的には「価格重視の購買」と理解できる。しかしさらに深掘りするとその背景には、「節約を美徳と考えている」「品質よりもコスパを重視する文化で育った」「高価なものに不安を感じる」といった価値観があるかもしれない…)
あなた「高くても良い商品より、安い方がいいのはなぜですか?」
また、「〇〇ということは△△とお考えなのでしょうか?」と、発言に内在する前提をこちらから仮定して問いかけてみるのも一つの方法です。
ただし、この場合は自分の推測を押し付けないよう注意し、「いえ、そうではなく…」と修正してもらうつもりで投げかけます。参加者が「そうです、その通りです」と同意すればその前提が確認できますし、「いえ、本当は○○だからです」と否定すれば、より正確な価値観を引き出せます。
発言の裏にある背景を探ることで、単なる事実ベースの情報から一歩踏み込み、参加者の価値観に触れることができます。それこそが他社にはない独自のインサイトにつながる可能性があります。常に「この人はなぜこう感じているのか?」と心の中で問いながら聞く習慣を持ちましょう。
8. 「過去の具体的体験」に注目する
インサイトを引き出すには、参加者の過去の具体的な体験談を詳しく語ってもらうことがとても有効です。
人は抽象的な一般論よりも、具体的なエピソードを話すときにこそ本音や感情が表れます。したがって、「普段は〇〇ですか?」と一般的な傾向を聞くよりも、「直近で経験した具体的なケース」をベースに質問を展開しましょう。
そこで語られた行動や発言を軸に「なぜそうしたのか」「そのとき何を感じたのか」を掘り下げるのです。
新製品に対する意見を聞きたい場合
「この製品についてどう思いますか?」といきなり問う
「実際に使ってみた中で記憶に残っている出来事を教えてください」「使ったのはいつ、どんなシーンでしたか?」など、具体的なシチュエーションを思い出してもらう
具体的な事実に基づいて質問することで、参加者自身も当時の状況をリアルに思い浮かべながら回答でき、より深い自己分析が促されます。
さらに「他にも同じような経験はありますか?」と尋ねれば、本人も気づいていなかった共通する動機パターンをセルフチェックするきっかけにもなります。
過去の体験を引き出すメリットは、回答に信憑性と具体性が増すことです。
人は未来のことや仮定の質問に対しては理想論や建前を語りがちですが、過去の事実は変えようがないので比較的正直に話しやすいものです。
「もし〇〇だったらどうしますか?」という想像の質問ではなく、「最後に〇〇したのはいつですか?どんなきっかけでしたか?」といった実際の経験談を聞くことで、現実に即した洞察が得られるでしょう。
具体的な体験にこそ人間の心理が表れる――この視点を常に持って質問を組み立ててください。
9. フレームワークを使いすぎない
インタビューの設計や分析には各種のフレームワーク(枠組みや定型的手法)が役立ちます。例えば質問リストやインタビューフローのテンプレート、分析用のカスタマージャーニーやペルソナ像などがそれに当たります。しかし、フレームワークに頼りすぎて融通が利かなくなるのは避けるべきです。デプスインタビューでは臨機応変さが求められるため、フレームワークはあくまでガイドラインと捉え、状況に応じて柔軟に変更・補足する姿勢が大切です。
例えば、事前に用意した質問ガイドに沿って進めるのは基本ですが、相手の反応に合わせて質問の順序を入れ替えたり、新たな質問をその場で追加したりするのはしばしば必要になります。
インタビュアーがマニュアル通りにしか質問しないと、せっかくの会話の流れを断ち切ったり、有望な話題をスルーしてしまったりすることがあります。一問一答の機械的なやり取りでは、深いインサイトは生まれにくいでしょう。「聞きたいことリスト」は絶対ではなく参考程度と捉え、対話の中で優先度の見直しや質問のカスタマイズを行いましょう。
また、分析段階でもフレームワークの弊害に注意です。例えば最初に決めたペルソナ像に当てはめるあまり、せっかく出てきた意外な意見を「ペルソナとズレるから」と切り捨ててしまうのは本末転倒です。仮説検証には軸が必要ですが、インサイト発見フェーズでは仮説やフレームに合わない事実も積極的に取り入れる柔軟さを持ちましょう。
要するに、フレームワークは上手に使えば思考整理に役立ちますが、使いすぎれば視野狭窄を招きます。デプスインタビュー本来の強みは自由度の高い対話から想定外の洞察を得られることにあります。その良さを損なわないよう、現場で得られた生の声を最大限活かすことを意識しましょう。
実践事例|インサイトを起点に商品開発が成功したケース
ここで、デプスインタビューなどを通じて得られたインサイトを起点に商品開発した実例を紹介します。インサイト活用の重要性を具体的にイメージするために役立ててください。
日清食品「カップヌードル リッチ」
日清食品が発売した「カップヌードル リッチ」シリーズは、シニア層向け即席麺という新たな市場を開拓し話題となりました。一見すると若者向けのイメージが強いカップヌードルですが、開発の背景にはシニア層の意外なインサイトの発見がありました。従来、シニア向け食品といえば健康志向で「体に良い」ことを売りにした商品が多く、企業側も高齢者は健康重視と考えがちでした。ところが、市場調査(デプスインタビューを含む定性調査)によってシニア世代にも揚げ物など「ちょっと贅沢な食事」を楽しんでいる層が一定数いることがわかったのです。
いわば「高齢者=健康第一」という前提の裏に、「たまには好きなものを食べて豊かさを味わいたい」という潜在ニーズが隠れていました。
日清食品はこのインサイトを「リッチ=贅沢」というキーワードで捉え直し、カップヌードルにフカヒレスープ味やすっぽん(高級食材)味といった豪華なフレーバーを展開しました。
健康志向ではなく嗜好性に振った商品コンセプトは当初社内でも驚きがあったようですが、発売すると「たまにはこういう贅沢もいいね」とシニア層に受け入れられヒット商品となりました。
この成功は、「シニア=健康重視」という表面的な常識にとらわれず生活者の隠れた本音を読み取ったことにより実現した好例と言えます。

Dove(ダブ)のマーケティングコミュニケーション戦略
ユニリーバ社のスキンケアブランドDove(ダブ)は「女性たちは自分の容姿に自信がない」という調査結果で、「自分を美しいと思う女性はわずか2%」という衝撃的なデータをインサイトと捉え、「本当の美しさとは誰にでもある」というメッセージのキャンペーンを展開して世界的な共感を呼びました。
これらは商品そのものだけでなくマーケティングコミュニケーションにインサイトを活かした例ですが、いずれも従来の思い込みを覆すユーザー洞察が成功のカギとなっています。
このように、デプスインタビューなどで得られた深い顧客理解は、新商品開発やプロモーション施策の方向性を大きく左右し得る強力な武器です。インサイトに基づいて企画を立てれば、競合も気付いていない隠れたニーズを満たす独自性の高い提案が可能になります。裏を返せば、インサイトなくしてヒット商品を生み出すことは難しい時代とも言えます。事例から学べるのは、ユーザーの声に真摯に耳を傾け、その奥にある本音を汲み取ることの価値です。
ぜひ自社の商品企画でもインサイトドリブンなアプローチを意識してみてください。
まとめ:デプスインタビューを活用し、消費者の本音を引き出す商品・マーケティング施策を実現しよう
消費者の深層心理や無意識の欲求を理解することは、商品開発やマーケティングにおいて極めて重要です。しかし、定量データだけでは見えてこない「なぜその選択をするのか?」という本質的な理由を探るには、デプスインタビューが欠かせません。
本記事では、デプスインタビューを活用することで得られるインサイトの価値や、実践的な手法について詳しく解説しました。デプスインタビューの結果を有効に活用するためには、単なる「消費者の声の収集」にとどまらず、それをどのように分析し、施策へ落とし込むかが鍵になります。
- 得られたインサイトを整理し、共通するパターンを見つける
- インタビューの中で発見した動機や価値観を分類し、ターゲット層の傾向を分析。
- 矛盾や意外な発言に注目する
- 言葉の裏に隠れた本音や、想定と異なる発言が重要なヒントとなることが多い。
- 商品開発やマーケティング施策に具体的に落とし込む
- 得られたインサイトを基に、商品コンセプトやプロモーションの方向性を具体化。
デプスインタビューを単なる情報収集の手段ではなく、消費者インサイトを事業成長につなげるための重要なプロセスとして活用することが求められます。
株式会社SEAMでは、自社の20〜30代向け低アルコールカクテル商品開発で培った実践的なノウハウをもとに、企業の新商品開発やマーケティング支援を行っています。
また、デプスインタビューの設計・実施・分析・活用の各フェーズでサポートが可能です。
- 「ターゲットの本音を知り、より響く商品を開発したい」
- 「定量データだけでなく、深い消費者インサイトをマーケティングに活かしたい」
- 「開発・クリエイティブ・プロモーションまで一貫してサポートしてほしい」
こうした課題でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。