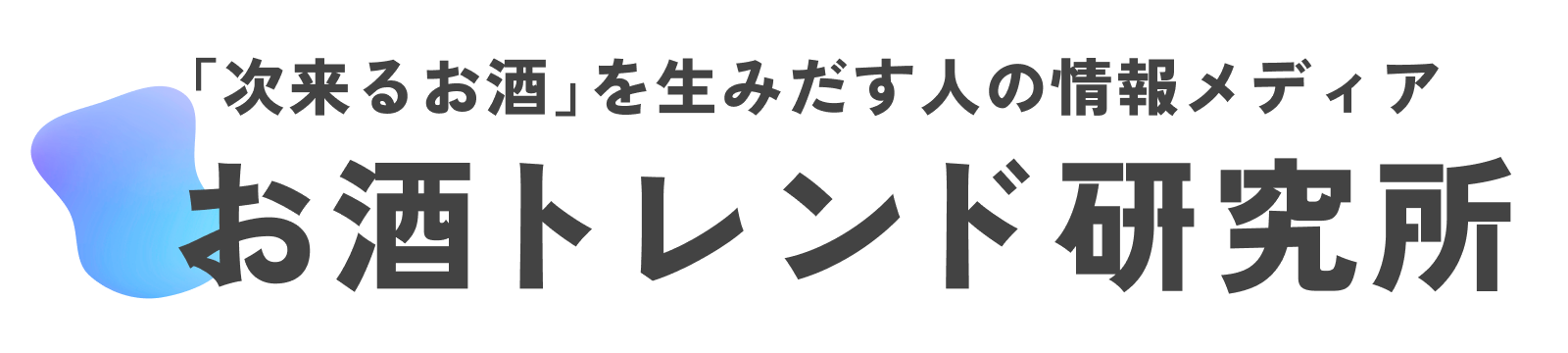Z世代が求める“手触り感”と“ノスタルジー”── 物性魅力を飲料商品に落とし込む方法
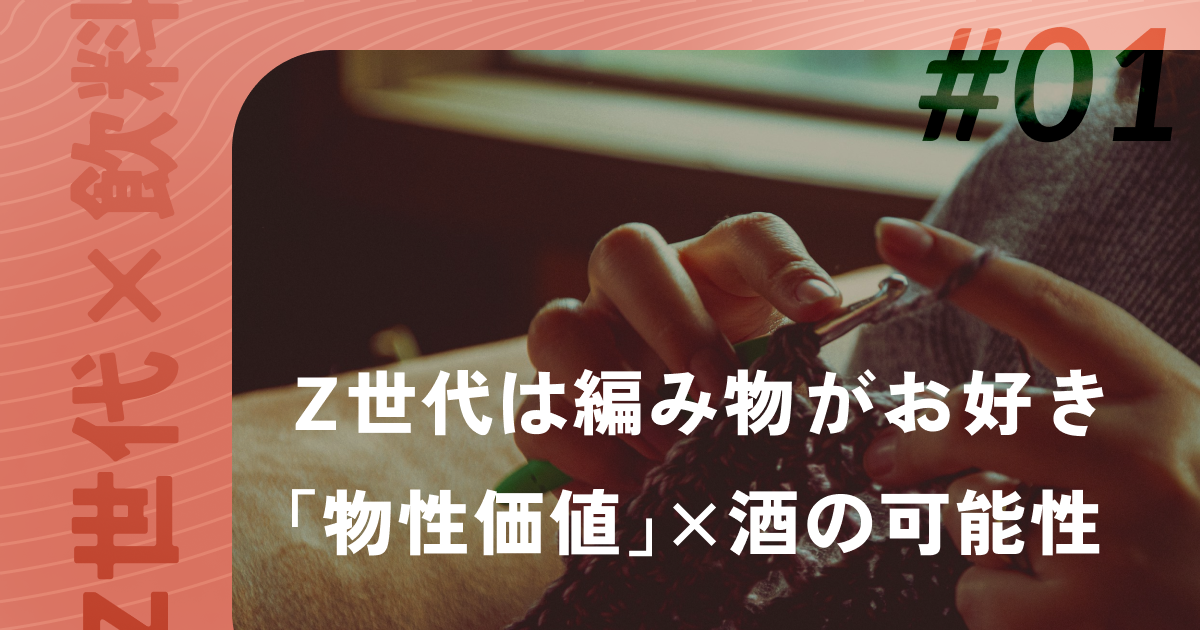
デジタルに慣れきったはずのZ世代が、なぜか「モノそのもの」に惹かれている──。
編み物やレコード、平成レトロなど、あえてアナログな感触を楽しむ若者の姿は、SNSでもたびたび話題にのぼります。こうした動向の裏には「物性魅力」と呼ばれる感覚の新しさが潜んでいるようです。
そもそも物性魅力とは、モノならではの質感や温かみ、手間のかかるプロセスから生まれる心地よさのこと。
まるで効率一辺倒の世の中へ一石を投じるように、Z世代は“デジタル全盛の時代だからこそ大切にしたいリアル”を求めているのかもしれません。
本記事では、彼らが物性魅力に魅せられる理由を掘り下げながら、飲料商品企画にどのように活かせるのかを考えていきます。
1. 物性魅力の正体とは?
物性魅力=“リアルな質感”が生む特別感
物性魅力とは、モノそのものが持つ物理的な質感や手触り、重さといった五感を刺激する側面を指します。
たとえば編み物であれば、糸の柔らかさや編み目の間から感じる空気の流れ、手間をかけて仕上げる過程の“無心”の感覚などが大きな魅力です。Z世代はデジタルでほぼ何でも済ませられる日常に慣れているからこそ、あえて触れることでしか味わえない感触を「新しい刺激」として受け止めているのです。

一方で「平成レトロ」や「たまごっち」のような一昔前のアイテムも、懐かしさと新鮮さが入り混じった不思議な存在感を放っています。過去のカルチャーを体験した覚えのある人は「懐かしい」と感じ、まだ体験したことのない世代には「逆に新しい」と映る。そんなギャップが、どこか特別な物理的存在として認識されているようです。
参考記事:
2. Z世代がアナログに惹かれる理由
しかし、なぜZ世代はアナログで物質的なものに惹かれるのでしょうか?
その背景には、単純な懐古趣味や流行以上に、デジタル社会への反動、過去へのノスタルジー、そして自己表現への強い欲求といった複雑な要素が絡み合っています。一つ一つ紐解いていきましょう。
デジタル疲れからの“反動”
スマートフォンやPCを介して、いつでもどこでも情報にアクセスできる便利な時代。
しかし、常にSNSやネットに接続していることで、心が絶えず刺激され続け、知らず知らずのうちに「デジタル疲れ」を感じているZ世代も少なくありません。そんな彼らにとって、編み物のような“手を動かす時間”や、レコードをセットしてじっくり曲を聴く“スローな行為”は、心を癒す特別な体験となっています。
短時間で完結するデジタルの効率性とは異なり、アナログな作業には「余白」が生まれます。
その余白の中で、モノの質感を味わい、ゆっくりと時間をかける行為が、Z世代にとっては新鮮でぜいたくな時間として映っているのです。
また、この“あえて時間をかける”行為そのものが、日常のストレスから解放されるためのセルフケアの一種としても認識されています。効率を重視する社会へのささやかな反抗心が、こうしたアナログな体験への憧れを後押ししているのかもしれません。
ノスタルジーと新しさの同居
Z世代を惹きつけるアナログな魅力には、過去へのノスタルジーと現代的な新しさが絶妙に交差しています。
平成レトロやY2Kファッションのリバイバルはその象徴です。
自分が子供の頃や両親世代が若かった頃のカルチャーを、自分なりに解釈して取り入れることで、「今っぽさ」と「懐かしさ」を同時に味わうことができるのです。
音質の良し悪しでは計れないレコード特有の“味わい”や、スマホでは再現できないデジカメの少し粗い画質は、「不完全だからこその魅力」として再評価されています。
こうしたローファイな質感が、デジタル完璧主義へのカウンターとして支持されているのです。さらにクラフトビールのように「地域性」や「作り手の思い」といった背景ストーリーがある商品も、デジタルでは得られないリアルな体験としてZ世代に響きます。Z世代は単なる商品以上の“物語”を消費しているのです。
自己表現としての物性重視
Z世代にとって、物性魅力は単なる「モノの魅力」にとどまりません。
それは自己表現の手段としても重要な意味を持ちます。
たとえば、編み物の写真をSNSに投稿することで、自分の感性やこだわりをアピールする。
あるいは、カラフルなデジカメをファッションアイテムとして持ち歩き、日常の中で自分らしさを演出する。
これらの行為はすべて、「自分だけのスタイル」を周囲に示すためのものとも考えられます。
さらに、Z世代は他者との“ゆるやかな共感”を大切にする世代でもあります。
K-POPアイドルが編み物を楽しんでいる様子をSNSにアップすれば、それを見たファンは「私もやってみたい」と感じ、同じ体験を通じてコミュニティの一体感を味わいます。こうしてトレンドは瞬く間に拡散され、従来の「アナログ=古い」という価値観を塗り替えていくのです。
つまり、Z世代にとって物性魅力は単なるモノへの愛着を超え、「自分らしさを表現し、他者とつながるためのツール」でもあるのです。デジタルの中に埋もれがちな個性を、あえてアナログなモノや体験を通じて示す。その行為こそが、Z世代ならではの自己表現の形だといえるでしょう。
3. 飲料商品企画にどう活かすか?
「平成レトロ」「編み物」「デジカメ」など、Z世代が夢中になるトレンドには共通する本質的な価値があります。
それが、“物性魅力”や“ノスタルジックな温かみ”です。
単なる流行の表層をなぞるだけではなく、この深層インサイトを捉えることが、Z世代の心をつかむ飲料企画を生み出すカギとなります。ここでは、その本質を理解したうえで、どのような商品設計が可能か、いくつかご紹介します。
①ボトルやパッケージを“所有して嬉しいもの”にする
パッケージデザインには、昭和・平成時代のグラフィックや配色を取り入れるだけでなく、あえて“不便さ”を感じさせるディテールを施します。
たとえば、開栓に少しコツが必要な仕掛けや、手に触れたときの質感が楽しめるアナログなラベルを採用することで、飲んだ後も飾りたくなる“所有する楽しさ”を提供します。Z世代は、単に商品を消費するだけでなく、その“所有体験”自体に価値を見出しているのです。
たとえば私たちのブランドkoyoiは、一件ロゴマークのみがついたボトルのデザインですが、飲んでいくと裏からラベルのイラストがみえる資料になっています。そして、飲み終わったあとも、花瓶や水差しにつかっていただいているお客様も少なくありません。このように、瓶をただ容器にするのではなく、特別なものに変換する仕掛けをしています。

②深いストーリーと作り手の思いを添える
クラフトビールがZ世代にも響いている要因として、「地域の素材や職人の技術が詰まっている」というストーリーの存在が挙げられます。飲み手はビールを味わうだけでなく、作り手がどんな思いで商品を生み出しているのかまで感じ取れます。それは“物語を手に取る”行為でもあり、結果的に「自分だけの特別な体験」として心に残るからです。
飲料商品であれば、原材料の産地から作り方、関わる人々のこだわりなどを積極的に発信することで、「物性に宿るストーリー」を届けることができます。
③懐かしさと現代性をうまく組み合わせる
「昔ながらのデザインで中身も昭和レシピそのまま」という商品よりは、「レトロなテイストをまといつつ、最新の健康志向を組み込む」など、懐かしさと現代性の両方を持ち合わせたアイデアの方が受け入れられやすい傾向があります。
見た目はノスタルジックでも、糖質オフやカフェインレスといった機能面をしっかり抑えていれば、Z世代のライフスタイルにより無理なくフィットし、長く愛される商品に育っていく可能性が高まるでしょう。
4. まとめと今後の展望
Z世代が物性魅力を好む背景には、デジタル全盛の時代に感じる疲れや、“あえて不便”を面白がる新しい価値観があります。それは単なるトレンドではなく、手間暇をかけることの豊かさや、目には見えないストーリーを共有する行為の尊さを再発見する動きとも言えます。
飲料商品企画においては、単にレトロ感を取り入れるだけで終わらせず、原材料や作り手の思い、時間をかけることの意味などをしっかりと“物語”として設計することが大切です。Z世代の興味を引くにはSNSとの親和性も大事ですが、本当に心をつかむのは、“質感とストーリー”を通して感じられる深い愛着なのではないでしょうか。
SEAMでは、自社ブランド運営を通して、若年層のお酒やドリンクに関する現状を調査・分析してまいりました。若年層向けの商品開発を行いたいがインサイトがわからないとお困りの方は、ぜひ気軽にご相談ください。